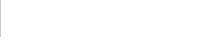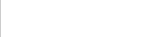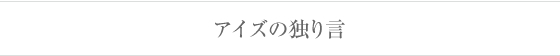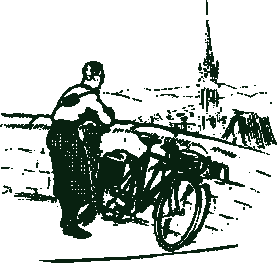フランス出張報告 -Alex SiNGER-
出発は2月28日でしたので、もうふた月近くも経ってしまいました。
帰国してからの慌ただしさといったら大変なもので、それでも、いくつかお伝えできることから書いてみようと思います。
世界的パンデミックのせいで止まってしまっていた、私たちの中の眠っていた部分というか、鈍くなっていた部分が、今回の旅でまた動き出したような気がしています。
今回は戦時下の国々の上空を避けてぐるっと逆回りでフランスへ向かいました。
なので搭乗時間は14時間!!! もう、私なんて3時間くらいでじっと座っているのが辛くなってくるんだけど、今回は一つ楽しみがありました。
アイスランド上空。(だと思う。)
一面氷の世界。(グリーンランドかな。)
明るい中、こんな景色が見れて純粋に感動しました。
で、フランスに到着したのは19時すぎ。
ほぼ予定通りでしたが、たくさんの荷物をすべて回収して税関を通過できたのがその1時間後。
サンジェのオリビエが迎えに来てくれているはずなんだけど、、、。
電話すると「え、明日じゃないの!?」なんて言われてビックリ。
というのも今年はうるう年で2月は1日多かったのが原因でした。私たちが来る日を「月末」で記憶していた彼がすっかり思い違いをしてしまっていたのでした。ちょっと最初から慌てましたが、なんとかすぐに車を飛ばしてきてくれて、その日の内にサンジェの店内に荷物を入れることができました。
1938年創業のアレックスサンジェ。
今も当時の店構えで自転車店として営業を続けています。
相変わらずのたたずまいに安心するやら、懐かしいやら。
3代目店主のオリビエ・シューカ氏。
私が初めて親方に連れられてサンジェのお店に行ったのが1996年で、親方はその数年前ですから、考えてみれば彼とも随分長いお付き合いです。
一緒に仕事に励んでいるのは息子のウォルター・シューカ氏。
今年で25歳。
オリビエの後を継ぐ決心をし、去年あたりからフルタイムで一緒に店に立つようになりました。
店奥のアトリエではフレーム作りの最中です。
フレームを作るための工具や治具も歴代の工夫が詰まった物ばかりです。
その傍らで親方は自分たちの自転車の準備をさせていただきました。
気が付くと、ウォルターが親切なことに親方のステンレス車のバーテープのニス塗に塗り足しをしてくれています。これは親方が自ら出発前に急いで仕上げたもので、少し薄めだったのがオリビエが気になったようです。
*****
さて、ラリーサンジェ。
今回で4回目の参加です。
毎年3月第一日曜日に開催されるこのラリーは春の自転車のシーズンインを告げるイベントでもあります。ですが、フランスのこの時期は毎回寒くて、過去に参加した3回の内2回は小雨降るなか走ったものです。今回も出発時は小雨。でも、中止になる事ってほとんど無いんですよね。
7時30分にサンジェのお店で待ち合わせ。
今回は14歳の少年を含むご家族2組とオリビエの奥様のカトリーヌが一緒に走ってくれました。
受付兼、スタート場所はパリ16区にあるポルトマイヨ。
スタート後はパリ市内を離れ、ブローニュの森へ。そして、ベルサイユ宮殿へと向かいます。
往路ではベルサイユ宮殿を裏(?)から眺められるベルサイユ公園を通り、
復路ではベルサイユ宮殿の正面を通りました。
一緒に写ってくれたのは今回一緒に走ってくれたフローレンスさん。
そして、こちらはオリビエの奥様のカトリーヌさん。
サンジェの自転車は650Bなら32B、700Cでも23Cや26Cが主流。
ホームページも是非ご覧ください。
今回の走行ルートはこちら。
ラリーの後はサンジェのお店で抽選会。
毎年、TAやストロングライト、べロックスにゼファール、ベルトゥサイクル、イデアル、もちろんグランボアもスポンサーとして景品を提供しています。
そして、アトリエは即席の立食パーティー会場と化し、ACBOのメンバーが走行後の歓談を楽しむ場となっています。
はい、今年もトロフィーいただきました。
いつもありがとうございます。
そして、更に昼食会。
この写真のほかにも参加者が30人ほどいたかな。お料理はシュークルートがメインのアルザス料理。なかなか豪快な見た目ですが、お味はあっさり目でとても美味しかったです。アルザスはサンジェのルーツでもあるので彼らにとっては郷土料理ですね。
*****
アイズバイシクルではアレックスサンジェのオーナーズミーティング”ランデヴーアレックスサンジェ Le Rendez-Vous Alex SINGER”の事務局を務めています。毎年5月第3土日は定例ミーティングです。
今年の開催日時は 2024年5月18日・19日(土・日)。
サンジェをお持ちの方、興味がある方でしたらどなたでも歓迎します。ご連絡いただけましたらミーテイングの詳細をお知らせしますのでお気軽にお問い合わせください。また、すでに会員方には案内をメールでお出ししています。参加表明はできるだけ4月末までにお願いします。また、メールが届いていないという方は至急お知らせください。
***
京王閣フリーマーケットに出展予定です。
移動日も含めて4月26日・27日はメカニック不在となりますのでご注意ください。
ゴールデンウィーク中は休まず営業予定ですが、閉店時間は18時までとなります。
そうそう、ランデヴーにはスタッフ全員で参加しますので、5月18日・19日はアイズバイシクルは臨時休業となります。
ご不便をおかけしますが、よろしくお願いします。
5年ぶりのフランスへ
このブログに先行してSNSでフランスから取り寄せた地図を前にプランニングしている写真をアップされてしまいましたが、今月末からのフランス出張が決まりました。本当に行けるかどうか、この直前の時期まで諸事情あるわけですが、なんとかクリアできそうとなり、一気に親方も私もソワソワと落ち着かなくなってきました。。
正確に言えば、2019年のパリブレストパリ/コンクールマシンに参加して以来なので4年半ぶりです。レートも高くて大変なんですが、いくつか棚上げになっていることもあるのでパリオリンピックが始まる前に行ってこようと思います。もちろん、行くからには自転車持って、ラリーサンジェールに参加して、ついでにツーリングもしてこよう!
もちろん、しばらく会えてなかったフランスの友人たちに会えるのも楽しみです。
出発は2月28日、前半は納車と引き取り、ラリーサンジェなどでパリ近郊で過ごしますが、後半はTGVでトゥールーズまで移動し、そこからカマルグ自然公園までミディ運河沿いを4泊5日で走る予定です。最初はロワール川沿いのお城巡りかな、と旅のテーマをお城にしていたのですが、ご来店いただいたフランス人のお客様から南仏のミディ運河沿いのルートもおすすめだよ、と教えてもらいました。調べるととても面白そうです。ミディ運河沿いはEV8 (ユーロベロ8) の一部として自転車道が整備されていますが、未舗装路の割合も高くランドナーで走るのが楽しそうなルートです。特にカマルグ自然公園はそのユーロベロからは外れますが、地形も独特なうえ、野生のフラミンゴが生息しているとのこと。更に2月から3月は繁殖期にあたり、ピンクのフラミンゴが見れそうです。
というわけで、今年の親方と専務が行く春の旅のテーマは「運河」と「フラミンゴ」。
旅の様子はいつものようにインスタやフェイスブックでまずはお伝えしますね。
今回の旅のプランも今年のカタログに紹介したやり方で親方が綿密に立ててます。
宿の手配やTGVの予約だけでなく、どこに見所があって、どのルートがより面白そうか、ここひと月ほど仕事の合間にを使ってすでに親方の旅は始まっています。
あと、2週間を切りましたが、サンジェのオーダーをご希望の方はオーダー代行も承ります。
是非、お気軽にお問い合わせください。
クリスマスセールにむけて
こんにちは、前野です。
17日(日曜日)はアイズバイシクル店頭でクリスマスセールを開催します。
今日は普段取り上げていないものを中心にご紹介したいと思います。
本題の前にブルべを走ってきたので少しだけレポートを。
先週末はBRM1209近畿300km京都に参加してきました。
平安神宮スタートで参加しやすかったので冬場のトレーニングを兼ねてエントリーしました。
コースは300km獲得標高3,000mと標準的。季節外れの暖かさで最高気温20℃、最低気温2℃の気温差と信号停止が多かったことが少々ハードでした。
使用した自転車は今年1月のハンドメイドバイシクル展で展示した速く快適に走るための650Bランドナー。300kmの道中殆どの時間を戦闘機のようなカーボンディスクロードに乗る友人と走りましたが、最後までペースを合わせて調子よく踏み続けることができました。
42Bタイヤでブルべを走っていると驚かれることがあります。そもそもランドナーという時点でハンディキャップを負っているように捉えられがちですが、この自転車はブルべを速く楽に走るために作りました。軽く転がり快適な42Bタイヤ、制動力が高くコントロールのし易いセンタープルブレーキ、無限に使える明るいライト、馴染んだ革サドル、手の平にフィットするランドナーバー。自分の自転車は伝統的なランドナーの様式を持ち合わせていますが、最優先事項は楽に走ることです。
今の自分は頻繁に走っているわけではないので、少しでも楽に進む自転車が必要です。練習を積み、身体的に優れていたらどんな自転車でもブルべを走れてしまうと思いますが、自分の場合は道具頼みなところがあります。そんなわけで、自分がランドナーで走っているのは少ない負担で長時間走れるからなのです。
今回はタイヤを変える時間が無かったので、未舗装林道を走ったアイズラリー2023の時と同じ丈夫な650×42Bエートル ルートフォレスティエールで走りました。650×42Bタイヤは豊富なエアボリュームのおかげで国道の荒れた路面でも良く転がり、登りでも大きな負担は感じません。もしタイヤを変える時間があればより軽量でしなやかなケージングの650×42Bエートル エキストラレジェを使って更に楽に走れたはずです。
トラブルなく順調に走って15時間6分で完走。良い1日になりました。
さて、本題の商品紹介です。
オンラインストアには掲載していない、アイズバイシクルの店頭にある商品を紹介します。
まずはこちら、Berthoud ASPIN Open
Berthoudの定番革サドルアスパンの穴あきモデルです。当店では通常取扱していないモデルになります。
中央の大胆なカットアウトにより尿道付近の圧迫を軽減し、革の柔軟性が増します。ロングライドを楽しまれる方、通常の革サドルではしっくりこない方いかがでしょうか。穴のない通常モデルのASPIN、ARAVIS、MARIE BLANQUEも在庫がございます。
お次はトピークのフレームポンプ、マスターブラスター。
スプリングのロック機能があるのでポンピングがしやすいフレームポンプです。
トップチューブ、シートチューブに取り付けたり、ペグがあればシートステーへの取り付けも可能です。
サイズS~XLまで4サイズすべて在庫があります。
こちらはシマノの片面SPDペダル、PD-ES600。
重量286gと軽量で、十分な耐久性があります。自分は旧モデルのPD-A600を数ペア、何年も使っています。
これのシルバーモデルがあればいいんですけどね…
最後はこちら。ここでヘルメットの紹介をするのはちょっと違和感があるかもしれませんがお許しを。
イタリアのヘルメットメーカーKASKの定番モデルMOJITO3です。
自分も昨年秋から被っていて、とても気に入っています。
欧州メーカーながら日本人へのフィット感の良さに定評があり、多くの方に被っていただけるはずです。
シンプルな形状と前後方向に延びる溝で風抜けが良く、長時間の着用でも快適です。
グレー/サイズM(頭囲52~58cm)のみ店頭にあります。
その他の色、サイズは取り寄せ可能です。(取り寄せ品はセール対象外です)
【アイズバイシクルクリスマスセール】
日時 12月17日(日)12時頃から18時頃まで
すべての店頭商品が店頭価格から1割引きとなります(※工賃は対象外です)
グランボアタイヤは通常時の店頭1割引きから更に1割引き!
今回紹介したほかにも、日東キャンピーフロントが久々に余裕のある数量入荷しましたのでオンラインストアに掲載しております。キャンピーのほかにもオンラインストア掲載品で店頭に並んでいない物もございます。オンラインストア掲載商品はもちろん店頭でも販売可能ですのでお声がけください。
遠方の方でクリスマスセール当日にご来店できないという方はオンラインストアのクリスマスセールをお待ちください。12月18日月曜日から24日まで開催します。
スタッフ全員で皆様のお越しをお待ちしております。
ブルべ:BRM909神戸600km
こんにちは、前野です。
オダックス近畿主催のブルべ「BRM909近畿600km神戸・乙・日本海と瀬戸内海」に参加してきました。
コースは神戸をスタート、三田、丹波篠山経由で北上して堀越峠、石山坂峠を経て日本海へ。
高浜から舞鶴、丹後半島の海岸線を走り、鳥取市へ。そこから一路南下して赤穂市からは瀬戸内海沿いを走って神戸に戻る600kmです。今年最初で最後の600kmブルべ。無事に走り切って今年もSRを確定させようと思っていました。そう思っていたんです…
前日に神戸へ
スタートが4:30と早朝で、京都から神戸まで自走で行くのは流石に遠いのでスタート近くに前泊します。
前日の昼過ぎに輪行して電車移動。帰宅時間帯と被らないよう早めに出たので神戸まで快適に移動できました。
宿の最寄り駅に到着
輪行解除して自転車を組み立てます。フォーク抜き輪行も回数を重ねるごとに手順が定まり、作業時間が短くなってきました。
自転車の準備が整うと、宿にチェックインする前にスタート地点の下見に行きます。
スタート地点近くを散策
輪行解除した駅から10分ほどで明日のスタート地点HATなぎさ公園に到着。港の景色と自転車を写真に収めます。明日のスタートは日の出前なので、明るい時間に神戸の港を見ることが出来て良かったです。
ちなみに、今回は輪行時の着替えなども全て自転車に積んで走ります。
輪行用の服として軽量なTシャツとハーフショーツ、インナーを1セット用意しました。コンパクトな着替えが1セット有れば走行中に運ぶ荷物の嵩を増やさずに、快適に輪行できます。
午前4時過ぎ、ブリーフィングと車検が行われる
早めに夕食を済ませ、20時過ぎに布団に入りましたが思ったほど眠れずに起床しました。
受付でブルべカードを受け取ってブリーフィングを聞き、車検を受けて4:30にスタートです。
4:30 スタート 神戸HATなぎさ公園
昨年から頻繫にブルべを一緒に走っている友人のSと、600kmブルべ初挑戦のH君の3人で走ります。
Sはカーボンディスクロードですが、H君は自分と同じく650Bランドナーで出走です。ただ、今回は600kmと距離が長くブルべまでに3人で一緒に走ることが出来なかったので、あくまでもペースが合えばの話です。
自分の計画は約30時間での完走。途中、ビジネスホテルなどで長い時間の仮眠をとる計画はありません。
SとH君は400km過ぎの鳥取市付近で仮眠場所を確保しています。もし2人と同じペースで走れば400kmくらいまでは話し相手がいて夜間も気が紛れそうです。
5:20 9km 通過チェック1 再度山公園入口
スタートしてさっそくガッツリ登ります。神戸ブルべ定番の再度山です。登りの序盤で装備が重いH君は後方に…
先は長いのでどこかで合流することに期待しつつ、Sと二人で淡々と登って再度公園の看板に到着しました。
ここでは通過証明の写真を撮ります。
7:28 朝霧の中へ
三田、丹波篠山と北上していきます。丹波篠山では霧が発生していました。これから雲海の季節。今年もおにゅう峠の雲海と紅葉を見に行く計画を立てたいところです。
9:33 約110km、南丹市美山
60kmほど走ったコンビニで一息つき、H君にも連絡を入れます。どうやら彼のペースで順調に走っているようです。
京都府南丹市下山から福井県高浜市までの区間は何度も走っています。美山の見慣れた景色の中走っていると、スタートから100km進んでいることに気が付いて驚きました。普段なら100kmも走れば満足ですが、今日参加しているのは600kmブルべ。ゴールまでの距離が長いと100kmも短く感じるものです。
10:11 128km 堀越トンネル
美山から緩やかに上って堀越トンネルに到着。ちなみにここは砂利道の旧道がお勧めです。
トンネルを抜けた先の福井県側はダイナミックな下りで一気に名田庄の道の駅まで下ります。
自分のランドナーのブレーキはグランボア シュエット3642 センタープルブレーキ。
36~42mm幅タイヤとそれに対応した泥除けをカバーするクリアランスを持ちながら絶対的な制動力が高く、ハイスピードな下り坂でもコントロールしやすいです。コーナー手前で一気に減速したり、当て効きによるスピードコントロールなど思いのまま。
新しい自転車の機敏なハンドリング、ハイグリップな650×42Bタイヤと相まって下りがとても楽しいです。
11:03 146km 石山坂峠を下る
堀越峠を名田庄まで下った後、緩やかに登り続けて石山坂峠(トンネル)に到着。
堀越峠と同じく、北側はダイナミックな下りでループ橋もあります。
気持ちのいい下りの途中には決まっていい景色があるのは何故でしょうか。
止まって写真を撮りたいけど、気持ちよく下り続けたい。そんなジレンマが有ります。
11:11 153.7km PC1 ファミリーマート高浜国道店
最初のコントロールポイントに到着。ここでは買い物をしたレシートの時刻が通過証明になります。
コーラと梅おにぎりで早めの昼ごはん。普段なら選ばない食べ合わせですがブルべ中だと最高です。フロントバッグに行動食を補充し、2本のボトルを満タンにして出発します。
13:07 190km 由良川橋梁
舞鶴の市街地を抜けて宮津を目指して走っていると由良川の河口にかかる由良川橋梁が見えてきました。
残念ながら電車が通る瞬間は見れませんでしたが、青空と日本海に映えるレンガ色の橋は一見の価値があります。電車を待ってカメラを構えている人もいました。
13:59 206km 天橋立
天橋立手前でアイス休憩をして、天橋立の砂利道区間を走ります。
土曜日で混み合っているので僕たちも観光気分でのんびりと進みます。
リフレッシュするために手袋を外して走る
トイレに寄った後、しばらくグローブを外して走ることにしました。
基本的にグローブは装着していますが、長時間走るときは手のひらをリフレッシュさせるために一時的に外すことが有ります。
日差し除けと汗留めを兼ねてサイクルキャップを着用
晴天で気温も高かったので縁のサイクルキャップをヘルメットの下に被りました。日差しを緩和し、汗を吸収してくれるので暑い日も快適です。
それに薄手のコットン生地なので通風性が有り、ヘルメットの中を流れる風を感じられます。
そして、僕とSのヘルメットの後部にはLinden BK-02が付いています。
5gと超軽量、超小型ながら充電式で光センサーによる自動点滅機能を備えたテールライトです。
綺麗な景色、経過は順調。完走は確実と思いきや…
天橋立を抜けると、舟屋で有名な伊根に向けて丹後半島の海岸線を進んでいきます。
きれいな空と海、普段とは違う景色が見れて「今日は最高の1日だ」と思いました。
平坦な道で交通量はそこそこありましたが舗装は整い、物を落とすような要因はありませんでした。
自分の失敗は天橋立で外したグローブです。
外したグローブを普段はスマートフォンを収納するジャージの背中ポケットに入れていました。グローブが詰まったポケットにスマートフォンを差し込んだところ、入りが甘く、スマホはポロっと落下しました。
後方を確認してすぐに停車。探しに戻ると当たり所が悪かったのかスマートフォンの画面はヒビだらけでまったく表示が出来ません。おまけに道路に落ちた後、さらに脇の水路に落ちて水に浸かっていました。
今回のブルべはレシート取得のコントロールよりも通過証明の写真を撮影する通過チェックが多く、写真は全てスマートフォンで撮影しています。
ここ数年はスマホのカメラの性能が良いのでデジタルカメラを持ってブルべに参加することは無くなりました。スマホが唯一のカメラでもあるので破損してしまうと致命的です。
SNSにバックアップを兼ねて通過チェック写真をアップしていたので、スタートからここまで一緒に走ってきたSとゴールまで共にすればどうにかなるかもしれません。ただ、もしSと離れてしまうと京都で待っている家族への連絡手段は公衆電話しかありません。それに明日ゴールできたとしても、明後日から日常に戻るのに電話が使えない状況はちょっと困ります。
理性的な選択は、ここでDNFして宮津に戻り今日の内に輪行で京都に帰ること。
わかってはいましたが、この時はまだ受け入れられませんでした。
14:50 224km 通過チェック2 伊根の舟屋
「スマホは壊れたけど完走目指して走り続ける」と、Sに言ってコースをそのまま進み、伊根の舟屋に到着。周辺は観光バスが多く停まり、一大観光地になっていました。
この写真は自分のスマホで撮影しました。壊れたはずなのに何故?
画面は写らなくなりましたが内部は無事でした。
音量調整ボタンと電源ボタンを利用した写真撮影を行うとシャッター音が鳴ります。画面が映らないのでその場で写真の確認は出来ませんが、後日確認すると写真は撮れていてクラウドに保存されていました。
Sに電話を借り、京都の妻にスマホが壊れたが明日のゴールまで走り続けることを伝えました。
幸い、財布に何かあった場合の緊急連絡先として電話番号を入れていたので連絡が出来て助かりました。スマートフォンに電話、カメラ、財布の機能を集約させていますが、アナログなバックアップは必要です。
丹後半島を走るのは楽しい。でも…
次の通過チェック経ヶ岬の標識を目指して丹後半島の海岸線を進んでいきます。
普段なかなか来られない場所なので走れる嬉しさ半分、このまま続けていいのかと悩む気持ち半分と言った具合です。身体の調子はいいので完走は問題ないと思いますが、いろいろなリスクを考えると頭の中はスッキリしません。
通過チェックを前にSがパンク
経ヶ岬の入り口までもう少しという所でSの前輪がパンク。何か異物が刺さったようです。
リムとタイヤの嵌め合わせが固いというのでタイヤの脱着を手伝い、素早く復旧。
16:00 241km 通過チェック3 経ヶ岬標識
パンク修理の場所から2~300mで通過チェックに到着。
経ヶ岬灯台の標識と自転車を写真に収めます。自分のスマホでは写真が撮れているかわからなかったので、Sに撮影してもらいました。
「このまま続けていいものか…」
明るいうちにDNFするべきではないかと何度も考えます。
19:00 296km 城崎温泉
琴引浜を通過し、丹後半島の海岸線が終わると暗闇の中峠越えをして城崎温泉に到着。
約300kmを14時間半なので、ここまでのトラブルや天橋立でのんびりしたことを考えると順調に進んでいます。
ちなみに城崎温泉でDNFすれば京都まで特急1本で帰れます。それにこの時間なら、普通電車で帰ることもできるでしょう。スマホが壊れたことを除けば快調に走れているので、この時は駅に向かおうとは思いませんでした。
20:56 324km DNF PC2ローソン香住バイパス店
城崎温泉を出発した後も淡々と走り続けましたが、PC2手前の海岸線で自分の自転車のチェーンが切れてしまいました。
正確には、チェーンが切れたのではなく、フロント変速の際にチェーンを詰まらせ、チェーンからテンションが抜けた拍子にミッシングリンクというチェーン簡易着脱用のコマが外れてしまいました。登り初めで少しトルクがかかった状態で変速を行った自分のミスが原因です。普段なら変速時はトルクをかけないようにするのですが、気が散っていたのでしょう。
このアクシデントで諦めが付きました。通信手段が無く、これから本格的な夜間走行なのにメカトラブル。晴れない気持ちのまま走り続けるのはさらに重大なトラブルを起こしかねません。
外れたミッシングリンクはどこかに飛んでいったので見つからず、いつも携行しているトピーク ラチェットロケットライトDX+のチェーンツールでチェーンを繋ぎなおして復旧しました。ちなみに、この工具はフルセットでは持たず、ラチェットハンドル本体、エクステンションバー、チェーンツールと自分の自転車に必要なビットのみ携行しています。
少し走れば香美町のPC2に到着です。DNFすることを決心したので足取りは重く、僅か数キロがとても遠く感じました。
PC2のローソンに到着すると、ここまで一緒に走ってきたSにDNFすることを伝え、電話を借りて宿の手配と妻に連絡をしました。宿が懸念事項でしたが何件か電話したところ、素泊まりが出来て22時までチェックイン可能な宿が駅の近くで見つかりました。
夕飯を済ませて出発するSにお礼を言って、自分は紙に写した道順を頼りにゆっくりと宿へ向かいました。DNFしましたが身体は元気で、自転車はチェーンを短く切り詰めたのでアウターローが使えないことを除けば快調です。
そんな状況で宿に入るとDNFでは無く仮眠休憩の為に入ったようですが、明日はもう走らないので時間を気にせず眠れます。風呂に入り、コンビニで買った夕飯を食べて、テレビを見て24時過ぎにようやく眠りました。
・
・
・
翌朝は早めにチェックアウトして、昨夜は暗くて見えなかった香美町の港を眺めてからJR香住駅へ向かいました。
駅前の公衆電話から主催者の方にDNFの連絡、妻にこれから帰ること伝え、約4時間のんびりと電車に揺られて京都に帰りました。
香美町まで一緒に走ったSは翌日にトラブルもあったようですが完走。序盤の再度山で分かれたH君は500km付近でPCの制限時間に間に合わずタイムアウト、DNFとなりました。
H君からブルべ後にホイールの相談を受けました。相談の結果、今後のブルべで余裕を持って走れるように軽やかに走れるホイールとエキストラレジェタイヤの組み合わせに新調してくれました。
10月末の姫路からしまなみ海道を往復する600kmに挑戦するそうです。頑張れ!!
今回は思わぬトラブルでDNF、2023年のSRを取り逃した形になりました。ブルべを完走出来なかったのは残念ですが、普段走らない丹後半島を満喫できたので悪いことばかりではありません。
来年も200~600kmのブルべを各1本ずつと、SR600を走りたいと思っています。いまは子供が小さく、家を空けるのが難しいのでなかなかブルべに出走が出来ませんが、長距離を走るのは楽しいので走力を落とさないように続けていきたいです。
・
・
・
【アイズラリーのお知らせ】
11月23日(木)にアイズラリーを企画しています。
京都市北部の京北と南丹市美山町の間にある未舗装林道を含んだ約50kmをみんなで走る予定です。
近日中に試走を行い、詳細はまた後日お知らせします!
ランドナーと共に四国フェリー旅(後編)
こんにちは、伊藤です。
つい先日大学時代の友人に会う機会がありまして、子供の保育園の話になりました。
朝は私が保育園まで送っています。ランドナーで送り迎えしていると言うとかなり驚かれました。

学生時代に乗っていたBSのアトランティス・スポルティーフ。THULEのチャイルドシートはシートチューブにマウントするかたちで後付けができます。ハンドルはアップハンドルにして街乗り仕様にしていますが、スタンドはつけていません。壁に立て掛けて子供の乗り降りをしています。妻は今時の電動アシスト自転車に乗っていますが、私は乗り慣れた自転車でないとしっくりこなくてこんな仕様で保育園まで通っています。子供を乗せる予定がないときはワンタッチでつけ外しができるので便利ですよ!
少し間が空いてしまいましたが、四国ツーリングの後編に入りたいと思います!
【石鎚スカイライン編】
山小屋の朝は早いです。
他に宿泊されていた登山者の方々の声で目が覚めました。

宿のご主人と話していると、
「これから黒森峠に行くの?」
「そうです。自転車の方はよくいかれるんですか?」
「そうだね~。結構しんどいよ~」
そうは言われても行くしかありませんので、ひとまず石鎚スカイラインの下りを楽しむことにしました。

早朝ということもあって上ってくる車はちらほらいましたが、下りる車はほとんどいなかったので爽快に下ることができました。逆に上るのは私的にはなしです(笑)

途中展望所があったので寄ります。

石鎚山がひょっこり顔を見せてくれました。目の前にそびえ立つ様はかなりの迫力がありました。
話が脱線しますが、

今回乗っている自転車については前編では一切触れていなかったのですが、実は自分で作ったフレームなんです。もったいぶりたかったんです、お許しください・・・
セミオーダーモデルTypeERは現在私が作っていますが、これは親方が図面をサイズごとに設計し、決められた枠の中で製作しています。フルオーダー車の醍醐味は「図面を一から引くこと」。CADを使い始め、出来上がっている図面から数字を拾うことからはじまり、親方が過去に作成した図面に片っ端から目を通し、まずは自分の自転車の図面を引くことを目標としました。引いては消してまた引くを繰り返し、なんとか形になったものの、自分がはじめて設計した図面からいざパイプをカットして寸法通りにフレームを製作することなんてできるのかと不安しかありませんでした。そんなこんなで少しずつ修正を加えながら自分の自転車の図面を温め続けていました。そして今年の1月のハンドメイド展で前野店長のブルべ車製作の話が舞い上がりました。製作は私。2本目に図面を引いた自転車が製作第1号になったというわけです。しかもそれは健脚な前野店長の自転車。私のフルオーダー一号目は彼に譲ることになったわけですが、自分で評価するよりも、私よりも何倍も自転車に乗る彼からの評価のほうが遥かに貴重です。ERフレームとは作る勝手が少し違いますから、「壊れませんように」と念じながらロウ付けしたことはここだけの秘密です。
そうしてほんの少しだけ要領を覚えて?製作したフルオーダー車2号目。それが今回のツーリングに乗りました32BフルオーダーERです。
自転車のテーマとしては「ライトキャンピング」
今までフルオーダーの中で作られていないような自転車、それが狙いでした。
オーダーらしさを出したくてタイヤは32B。TypeERでは36B~42Bが適正サイズなので32Bはオーダーしなければつくれません。タイヤが小さいのでその分肩下寸法が短くなり、シートチューブ芯ー芯で520のフレームですが、小ささを感じさせないそんなジオメトリも狙いでした。そして荷物もそれなりにしか載せないのであれば32Bで十分であろうとも思ったわけです。
パーツ構成は自分の持っている部品でライトキャンピングにふさわしいであろう部品をチョイスしました。一番の目玉は変速機一式のユーレ・ジュビリーで、これはアレックス・サンジェから外したもの。ジュビリーのイメージとしてはスポルティーフについている印象なんですが、これをキャンピング車で使ってやろう!というのが最初の目論みでした。よく壊れるという話を耳にしますが、今までまともに使ったことがないので私の実体験ではまったくありません。壊れるまで使ってやる!と意気込んでいる現在ですが、他の変速機にしれっと変わっていたらお察ししていただければと思います(笑)
それと、もちろんジュビリー用シフトアダプターを組み込んでいますので引きもバッチリ!
乗った印象としましては、乗り味は非常に軽かったです。ジルのセパレートパニアであれば操作性もいいですし、下りのコーナリングは絶妙に楽しかったです。もう少し重い荷物を載せるのであれば32Bでは少し細いかなとそう感じました。
私個人的には「ライトキャンピング」というテーマにふさわしい一台が完成したと、そう感じることができたと思います。


あっという間に石鎚スカイラインを下ってしまいました。
【いざ黒森峠へ】
石鎚スカイラインから県道12号を更に下ります。途中に「おもご ふるさとの駅」に寄り、昼食を確保。このあたりにコンビニなどは皆無なので貴重な補給ポイントです。
黒森峠を目指すため、国道494号を北上します。
地図を見ていると、面河ダムの西側を抜ける県道153号がおもしろそうだったのでそちらを通ることに。国道494号線自体車の交通量は限りなく少なかったのですが、さらに交通量の少ないであろう県道153号から北上し、国道494号に再び合流することにしました。

(県道153号へ合流するため宝来橋の手前で左に)

小刻みにアップダウンがあり、何よりも木々のおかげでとても快適に走ることができました。

再び国道494号に合流。ここからおおよそ300mUPで黒森峠です。

宿のご主人からしんどいと聞いていたものの、思いのほかすぐ上れてしまった印象でした。声を大にして今言いたいこと。瓶ヶ森林道のほうが何倍もしんどかったです(笑) 2人に置いていかれて一人でちんたら上っていたんですけどね・・・・


東温市側へ下る道は展望抜群、気持ちの良い下りでした。約15kmの800mDOWNの下り道はひたすらに下ったという印象で、黒森峠は久万高原町側から上ることを強くお勧めいたします!
後は海抜0mの東予港まで下るだけでしたので記憶がほとんどありません(笑)
時間もかなり余裕がありましたので、温泉施設で疲れた体を癒し、地元の食堂やさんで打ち上げとまではいきませんが晩御飯をいただき、フェリーターミナルへ。

I君とはここでお別れ。彼は車で来ているのでそのまま積載しますが、私たちは帰りもフェリーなので自転車をそのままフェリーに乗せたいところですが、大阪南港に着いてからも電車で輪行ですし、なによりも輪行状態でフェリーに乗せれば料金はかからないので、心を無にして輪行します・・・
22:00 東予港を出発し翌朝大阪南港に到着。
後は電車で京都に帰るだけなので、少し船内で休憩した後帰路につきました。

無事花園駅まで帰ってこれました。行きのときは急いで電車に飛び乗ったので写真なんて撮る暇なんてありませんでした。
今回の久しぶりのツーリング、UFOラインは霧との闘いでしたが天気に恵まれ、自分の造ったランドナーで走れて最高でした。一緒に行ってくれたT君とI君には感謝しています。
あれこれ妄想しながら自転車を作る時間ももちろん好きなのですが、できた自転車でどこに行こうとプランを練る時間も最高の時間でした。行きたい所はまだまだたくさんありますので、この32B ERランドナーと共に駆け回りたいと思います。